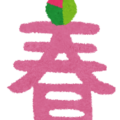曲概要
「久堅の幹」は長生淳の吹奏楽曲です。
中央大学吹奏楽部の第 50 回定期演奏会記念で委嘱されました。
この曲の推しポイント!
この曲は「C」で始まり、「C」の主題によって進み、「C」へと集約していきます。
その「C」とはドイツ音名の「C」であり、コードの「C」であり、中央大学の「C」です。
ちなみに僕が個人的に一番好きな調であり、音でもあります笑
「久堅」という言葉は現代日本ではあまり用いられる言葉ではありませんね。
古文において、「天」に関係する言葉(空、月など)にかかる枕詞として用いられています。
由来については「天」を永遠に堅固な物として捉えたという説、極めて遠いところにあるから(久方ですね)という説などがあります。
また、転じて「都」についても天上の物として捉え、永遠に続く物としてこの言葉が枕詞として用いられることがあったようです。
100年以上にもなる中央大学の歴史、そして50周年の吹奏楽研究会。
それらの歴史の積み重ねから天を久しく、確かな物とする「幹」を連想しました。
そこから「久堅の幹」という言葉が誕生しました。
標題音楽ではないので、この場面、この場面とはっきり移り変るわけではありません。
むしろ、A.Clを中心とした「C」の音で始まった曲は、川や時の流れのように穏やかに流れ続けます。
そういった印象を抱くのは三拍子を基調としていることにも起因するのかもしれません。
「心臓のリズムが三拍子だから、三拍子を聞くとリラックスする」
という説もありますよね。
しかし、そんな曲の中で特筆すべきなのはTp.のソロでしょう。
この緊張感の中、Tp.という楽器で吹くには一見リスクが高いようにも聴こえます。
しかし、この外すかもしれないという緊張感のあるTp.の音が良いんですよね。
Tp.じゃないといけないソロです。絶対に。
最後はチャイムが鳴り響く中、非常に華やかな雰囲気で終わります。
ここでいつも、「ああ、この曲は祝典的な曲だった」ということを思い出します。
長生淳という作曲家の入り口としてポピュラーなのは四季連祷とかでしょうか。
僕はこの曲でした。
もちろん後に聴いた他の曲も好きだったし、一番好きな作曲家ではあるのですが……。
この曲が一番好きです。
曲情報
曲名:久堅の幹
作曲者:長生淳
作曲年:2007年
この曲を一言で言うと:渋谷の女子高生に聞いた好きな吹奏楽曲は?アンケート一位獲得(俺調べ)
演奏歴:なし
(早稲田吹奏楽団での演奏歴:早、フィエスタ・ウィンドシンフォニーでの演奏歴:F)
Tuba.T